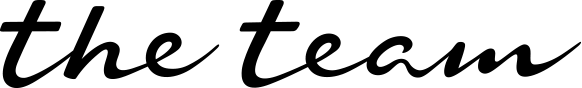1.ブランディングの進化の流れ
ブランディングの歴史は、企業や商品の「識別」から始まり、
「ブランドイメージ」「ブランドエクイティ」「ブランドアイデンティティ」「ブランドイノベーション」そして多様なステークホルダーとの共創による「ブランドコミュニティ」へと、時代ごとに焦点を変えながら進化してきました。
2.現在におけるブランディングの難しさ
近年はテクノロジーの発達により、企業がブランドイメージを一方的にコントロールすることは難しくなってきました。誰もが情報の発信者になれる今、ブランドの価値は、生活者やステークホルダーの多様な言動が複雑に融合した結果として形成・変化していきます。
企業として、どのようなブランドになりたいかという意思をブランドの「設計図」として描き、それを元に一貫性のあるブランディングを実践することはとても重要ですが、企業がブランドを自分たちの思い通りに完全にコントロールすることはできず、時には、一部の声によってブランドがいとも簡単に信頼を失墜してしまうこともあります。
このような複雑な状況下で、どうすれば多様なステークホルダーから、長期にわたって支持され、応援されるブランドになれるのでしょうか? そのためには 何が必要なのでしょうか?
結論から言うと、ここに、「企業人格」という、新たなブランディングの鍵があり可能性があると、私たちは考えています。
3.これからの鍵 : 「企業人格」
ブランドに「熱量」はあるか?
私は、長らく多くの企業のブランディングやブランドマネジメントに関わらせていただく中で、強いブランドには共通して「熱量」があると感じています。例えば、様々なブランド力ランキングで上位にあがるアップルに、皆さんは単なる製品以上の「熱量」や明確な「人となり」を感じないでしょうか? それはブランドの温度感といってもよいかもしれません。
昨今、企業が自社の社会的存在意義を表明する「パーパス」の必要性が注目されていますが、ステークホルダーからの深い共鳴を獲得するには、パーパスだけでは十分とは言えません。パーパスに加えて、「そのパーパスを、どういう人格で実現していくのか」という「人となり」がセットで伝わることが重要ではないか、と思うのです。(パーパスについては、 「人と組織と社会の可能性が開花するサステナブルなパーパス」をご参照ください)
ともすると、パーパスは抽象度の高い言葉に集約される傾向もあり、どのブランドも似通った言葉に見えることがあるかもしれません。しかし、それを体現する企業人格、つまり「人となり」は唯一無二であり、二つとして同じものはありません。ブランドの独自性を作り上げる源は「人となり」と言っても過言ではありません。
個々の製品やサービスでの差異化が難しくなってくる昨今では、この独自性の源たる「企業人格〜人となり〜」に共鳴してくれるステークホルダーとの紐帯をいかに構築できるか、ここが、ブランディングの焦点になってくると考えています。
4.「ブランドパーソナリティ」と「企業人格」の違い
これまでも、ブランドを「かっこいい」「優しい」「力強い」「ナチュラルな」など形容詞でイメージを定義する「ブランドパーソナリティ」という概念がありました。ブランドの世界観をトーン&マナーとして定義する「ブランドパーソナリティ」は、他社ブランドとのポジショニングの違いをわかりやすく伝える手法として有効に機能します。
しかし、これから支持され応援されるブランドに育てるには、それに加えて、ブランドの”内面”〜魂、態度、文化〜こそを明確に伝えることが、多くのステークホルダーからの共感を得る鍵となります。
もう一つ、多くの企業では、行動指針やValuesを定めていますが、それが単なる”定義”で終わり、一人一人の社員が実感や共感を持てていないケースも少なくないのではないでしょうか? 大切なのは、そこに社員一人一人、自分を主語にした「熱量」を込めることだと思うのです。
5.人はどんな人やもの、ことを応援したくなるか?
シンプルに考えてみます。人が何かを、誰かを応援したくなるのはどのようなときでしょうか? 例えば、スポーツの応援に私たちが熱くなるのは、そこにアスリートやチームの魂があふれださんばかりに感じられるからではないでしょうか? 頑張っている人を応援したり、そうしたストーリーに心を打たれるのは、そこに心の機微を感じるからではないでしょうか?
企業ブランドにも同じことが言えると思います。今、どれだけ「熱量」を感じるブランドが世の中にあるでしょうか? ブランドが長年続いていく中で、だんだんその「熱量」の輪郭がぼんやりしてしまったり、あるいは熱い魂はあるのに、それを上手くステークホルダーに伝えきれていない、そんなブランドも増えているように思います。
だからこそ、今改めて「企業人格」を明確にし、もっと顔や人となりが見えるブランドづくりこそが、次のブランディングのテーマになっていくのです。
6.社員の視点からも「企業人格」の明確化が求められている
多くの企業から、パーパスを掲げたものの、社員に “自分ごと化”されず、パーパス浸透がうまくいっていないと言う課題をよく伺います。この課題を解決する方法の一つとしても、「企業人格」は有効に機能します。
社員一人一人がパーパスを自ら形にしていくには、日々の業務の中で、どんな態度や振る舞いが求められるかの、より具体的な判断軸が必要です。この判断基準となる価値観・態度を「企業人格」として言語化するのです。
これは、社員一人一人の主体的な行動に一貫性と活力を生み出し、ブランドの内側からの強さを支える力になります。そして、このブランドがどんな価値観や考え(戦略)を持ち、どんな行動を取る人なのかという「企業人格」を、社員のみならずお客さまをはじめとするステークホルダーに分かりやすく「実態」と共に伝えていくことも、自転車の両輪として、もちろん重要です。
企業から発信される情報や施策が広がれば広がるほど、その参照点となる指針としても「企業人格」は機能します。まさに、「企業人格」は、内から外からパーパス経営を支える補助線とも言えるでしょう。
7.「企業人格」における経営者の役割とは
人に性格があるように、企業組織にも性格があります。そうした企業人格は、当然、経営者だけでなく、社員一人一人の言動が結集して形作られることは言うまでもありません。冒頭で、ブランドを企業が完全にコントロールすることはできない時代になったと申しあげましたが、「企業人格」をどう作り上げていくかは、十分に自分たちでコントロールできることだとも思うのです。
企業人格における経営者の役割は、次の2点に集約されます。
一つは、「経営者としての自分自身と、社員の大切にしている価値観の両方に真摯に耳を傾ける」という点です。どんな思考や考え方の特徴があり、判断基準として何を大切にしているのか? どんな強みがあり、どんな行動パターンをとっているのかなど内省していくと、自分たちが本当に大切にしていることは何なのかが浮かび上がってきます。経営者は、自分の思いはもちろんのこと、社員が大切にしていることも加味した上で「企業人格」を語っていくことが重要ではないかと思います。
もう一つは、「経営者が実際に発する言葉と態度」についてです。経営者が自己一致して、企業人格をどのような言葉で、一貫してどのように語るのか、そしてその言葉と行動に乖離がないかによって、企業価値は左右されます。経営者の言葉は、社員には意識・行動を形づくり文化形成の源泉になりますし、お客さまをはじめとするステークホルダーとは、感情的な結びつきを生み出します。強いブランドには、必ずその根底に「強い言葉とストーリー」があると思います。
8.企業人格を明文化する
以上をふまえてまとめると、企業文化の明文化する際は、次の視点が重要です。
①経営者・社員の言葉を融合させる
経営者の語る戦略、ビジョン、そして社員が大切にしている価値観や願いを統合します。
②活動を照らす「人格の軸」をつくる
企業人格として、当然いくつかの特徴ある性格の組み合わせになりますが、あれもこれも盛り込むと、結局どんな人なのかが見えなくなってしまいます。 事業や発信がバラバラに散逸しないように、事業活動の実態とも照らして「自分たちはどんな人格なのか」と立ち返れる参照点にしていくことが重要です。
③抽象的ではなく具体的に書く
行動の判断軸として機能させるため、何のために、何を、どうするのかという具体性が大切です。その時、自分自身の内的動機を起点に考えることが重要です。
④ストーリーで伝える
明文化した企業人格を実際のエピソードを持ってストーリーで伝えます。具体的なストーリーにすることで、企業人格として伝えたかったことの理解が深まり、かつストーリーは聞き手の感情移入をもたらします。
結びに : これからのブランドが問われるのは「人となり」
繰り返しになりますが、多様なステークホルダーから長期にわたって支持され、応援されるためには、事業活動を生み出すブランドの根っこにある「魂」や「人格」が重要な役割を担います。ブランドの“人となり”を明確にし、自己一致して実直に語り、実践していくこと。それこそが、これからの時代にふさわしい、企業ブランディングのあり方と言えるでしょう。