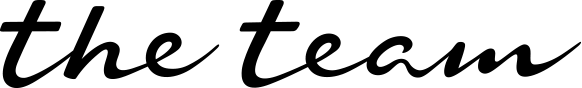1.共創・創発プロセスの企業経営にとっての意味
2011年にスタンフォードソーシャル・イノベーションレビューにて発表された論文「コレクティブインパクト」は、10年間で100万回以上ダウンロードされるなど大きな反響を生み出しました。
コレクティブインパクトは、異なるセクターのプレイヤーたちが領域を超え創発することで、社会問題などに対して生み出す成果のことを指します。大規模な社会変化をもたらすのは、個々の組織による個別介入よりも、セクターを横断する優れた連携であるという考え方や研究結果がその前提にあります。
言うまでもなく、ESG経営の重要性が増す中で、このコレクティブインパクトの概念の理解や能力は非常に高まっています。さらに、こうしたセクターを超えた共創・創発プロセスのデザインは、社会問題解決のために特化した手法や概念としてだけではなく、組織がイノベーションや創造性を発揮していく力や、従業員の本質的な働きがいを高めていく経営にとって、根本的に関わってくると、わたしたちは考えています。
2.次世代組織に求められる能力:コレクティブインパクトの創出
コレクティブインパクトは、平たい言葉でいえば、互いの利害を乗り越えながらコミュニケーションし、共通のビジョンとアジェンダを設定し、データに基づき学習しながらアクションを進捗させていき、創発的な成果を出していくことです。
コレクティブインパクトのプロセスの構造
(注1)SSIRコレクティブインパクトの新潮流と社会実装
- 集合的に問題を定義し、その解決のための共有ビジョンを描くことを通じて、生み出す共通のアジェンダ
- 継続的な学び・改善・アカウンタビリティにつながるような、進捗を追跡し共有するための共通の評価・測定システム
- 成果を最大化するために、参加者たちの多くの異なる活動を統合する相互に補強し合う取り組み
- 信頼を構築し、新たな関係を生み出す継続的なコミュニケーション
- 全体の動きを連携させ調整するバックボーン組織
こうした共創プロセスにおいて、個人や組織にとって本当に意味のある重要なことは、その成果というだけに留まらず、関わった組織や個々人が、ものごとをシステムとして捉え、システミックなチェンジを思考し実践的な体験をするということであると強調しておきたいと思います。
システミックなチェンジとは、関わるメンバーや組織が、自分自身が持っているこれまでの価値観や世の中を理解する背景となる物語(ナラティブ)や世界観の捉え方に変化が起きることで、ステークホルダーとの新たな関係の結び直しや、結果としての根本的なレジームシフトが生み出されることです。
(注1)SSIRコレクティブインパクトの新潮流と社会実装
この今ある前提を問い直し、ゲームチェンジを発想し社会実装として生み出すことは、今の企業に必要とされている非線形のイノベーションや創造性そのものですし、メンバーにとっては高い視座を得ると同時に難易度の高いチャレンジと本質的な働きがいが結びつくことにもつながります。
共創・創発プロセスを、重視することは、ESG時代の経営にとって現実的・実質的に重要であると同時に、実は、イノベーション創出や人的資本経営の観点からも非常に大切で着目すべきことであるともいえるのです。
さらに、今後は複数の企業が集うコレクティブブランドの概念も重要になってくるかもしれません。
3.共創・創発プロセスの要諦
ここでは、共創プロセスに関して私たちの研究と実践知から要点を要約しておきたいと思います。
① コミットのあるマイクロコズモ(小宇宙)チームの集合形成
共創・創発プロセスのデザインにおいて最も重要なことはそのメンバーと言っても過言ではありません。
旗をあげる主体者と、その熱意に賛同共感しシステミックチェンジに必要となるステークホルダーメンバーの集合が必要です。セクターにおける権限もある程度、有していることも重要です。
現実的には、必要なメンバーを事前に想定できること自体が難しいことですし、セクターにおける権限とコミットメントを持っているメンバーをリクルートすることは困難を極めますが、100%理想的にはいかずともそれを目指す努力が必要となります。
② チームがシステム全体を見るためのラーニングジャーニー
メンバー全員が、自らが関わっているシステム全体を理解し共有していくための学びの旅へのスタートです。メンバーそれぞれは自らの属するセクターにおける知識のプロであったりその最適化の視点を有しているものの、誰も全体システムを理解している者はいないと考えてよいでしょう。「現状の捉え方」自体が異なっていることはよくあることです。
メンバー全員で何を、どのように見聞きし学んでいくべきかの設計デザインが重要となるのです。答えは一つではないですが、道しるべとして、次のことが肝要であると我々は考えています。
- 1時間軸、2空間軸、3自分―世界軸でのアウェアネス視点です。
- 時間軸とは、過去〜現在の歴史を見ていく視点で、現在の問題や課題だけに囚われていると見えてこない長期の時間軸に現れるパターンを発見することもあります。
- 空間軸とは、空間的なランドスケープで捉えていく視点です。例として、海で起きている問題を山や川の流域全体のシステムで捉えていくとシステムとして見えてくるなどがそのわかりやすい事例です。
- 自分―世界軸とは、個人の内的動機と組織システムと社会システムの関係を丁寧に扱い、つながりを捉えていく視点です。大きな社会問題や大規模なイノベーションをテーマに扱おうとする場合、そのテーマが大きいほど、人一人の動機や想いを押し殺してこの大きなテーマの解決や実現の方を重要視していくようなことはよくあります。
- 関わるメンバーが自分自身の価値観にもアウェアネスを持っていること、それをメンバーで共有していることなどが、システミックなチェンジをおこしていくチームビルティングの上で、非常に重要な要件になっていきます。
- また、個人の内的な動機―組織―社会とのつながりのように、ヒューマンセントリックにシステムとして捉えていくことも、システミックなチェンジを考えるうえで非常に重要なことになります。社会問題解決やイノベーションが達成されたとて、個人が犠牲になっては本末転倒です。個人と組織と社会のBIG well-beingが実現されるためにもこの観点でのラーニングデザインは重要になります。
③ 未来への跳躍アクション
チームが、信頼関係を築きながら、システム全体を理解し共有した先に、未来へのアクションを生み出すステップです。
ここにおいては、現状のシステムからの変革を起こすために、リスクや痛みを伴いながらも、チャレンジしていく決断が必要になってくるフェーズです。
起こり得る外部環境に備えるのではなく、外部環境と言われるもの自体を自分たちで創り出そうとする意識で、共創出来る仲間とともに本当に成すべきこと、成したいことを見出していくことが肝要になります。
伝統的なシナリオプランニングを進化させたトランスフォーマティブ・シナリオプランニングなどは優れた手法です。
また、アクションや事業においては、アクションプランやにおいては、個人と経済と自然環境と社会を統合的に考え同時に向上させていくBiG well-beingとも言える思想や思考が重要になってくると言えます。
4.実際のケース
私達が、これまで取り組んできたケースをご紹介します。
■ 未来教育会議
未来に向けた教育に関するビジョンを多くのステークホルダーが参加し、共有・議論し、アクションを創発的に生み出していくことを目的としたプロジェクトです。<代表:熊平美香氏(現中教審メンバー)>
民間企業、官庁、教育委員会、学校関係者、NPO、アカデミアなどが参集したマルチステークホルダープロセスのための、ラーニングジャーニー、トランスフォーマティブシナリオ・プランニングなどのアプローチによって有効なコレクティブインパクトを生み出すことに成功しました。
https://miraikk.jp/
■ フードロスチャレンジプロジェクト
日本で最も早く自発的にスタートしたフードロスに関する初のマルチステークホルダープロジェクトです。<初代代表:大軒恵美子氏(元FAO日本職員)>
マルチステークホルダープロセスによるチーム組成と、バリューチェーンを巡るラーニングジャーニーとから生み出されたアクションのうち、2つは日本グッドデザイン賞を受賞しました。また、東京都との共同事業の結果によるアウトリーチは金額換算で8億円に相当する啓発PR効果を生み出しました。
http://foodlosschallenge.com/
■自動車会社 A社
某自動会社が初めて電気自動車を市場にローンチする際に、「新しいクルマ」としての宣伝・販売手法を取らずに、共創的なマルチステークホルダープロセスを採用したケースです。
行政、NPO、ユーザー、メーカー開発部門が集い、「動く電池」はどのように街をよりよくすることに貢献出来るか?という問いを、コレクティブに考え発想しあったプロジェクトです。これまで困難と考えられていた、行政、NPO、企業のコレクティブな共創の可能性を現実のものに出来たことと同時に、ビジネスとしても一切のテレビ広告などを使用しなかったにもかかわらず、アプローチがメディアから非常に高い評価を受けることにつながり、ローンチとしても高い成果を実現しました。
■ Imagine YOKOHAMA
開港150周年を迎えた横浜市が市民参加型都市ブランド構築事業として、新たな横浜のビジョンを策定したプロジェクトで、多くの市民が実際に参画したプロジェクトです。
1000名の市民ボランティアを募り、未来の横浜について語り、そのうちまた200人の近い市民がファシリテーターとなり自身のコミュニティで横浜の未来についてのワークショップを展開しその集約として横浜のマークやスローガンが策定されました。市民参画の都市ブランド作りとして稀有なプロジェクトしての評価を受けました。
5.結び
今後、複雑化していく社会においては、コレクティブなインパクトを生み出すためのマルチステークホルダー共創プロセスがますます大切になってくることでしょう。デンマークなど北欧の国では、クワトロヘリックスと呼ばれるセクター間の共創プロセスに関する概念が存在していてよく機能しています。
そしてこれらの共創プロセスに企業が関わることはコストではなくむしろイノベーションを生み出す人材育成や知恵や知見になっていくのであるということを強調しておきたいと思います。