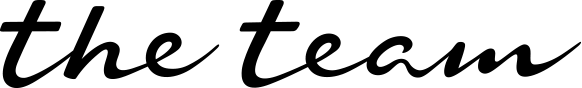【イベントレポート①】
現場から“学習する組織”へ──共感・自走・学習が支える花王ヘアケア事業のトランスフォーメーション
― 花王株式会社 野原聡氏 キーノート講演より(the team building day 2025)

最初のキーノートとして、花王株式会社ヘアケア事業本部の野原聡氏がご登壇。
「共感・自走・学習」が支える組織変革によるイノベーションの実践について、ご自身の体験に基づいたリアルな視点からのお話をいただきました。
「誰も来たがらない部署」で始まった挑戦
野原氏がヘアケア事業を担当することになったのは2023年。
当時の部署は9年連続で市場シェアが下落し、社内でも敬遠される空気があったと言います。
そこからわずか2年半で、6つのブランドをリブランディングまたは新規立ち上げに成功。
その裏には、“商品をつくる”ことの奥に、“組織そのものを再構築する”という大胆な変革のプロセスがありました。
ブランドの再定義とWell-beingへの転換
花王ヘアケアの新たなビジョンは「髪の生きる力を、人の生きる力へ」。
これは、単なる髪の機能改善ではなく、人の内面と日常を豊かにするというWell-being志向の価値転換です。
マーケティングの設計においても、機能や価格といった外的要素だけでなく、「その商品を使ったときの感情」を出発点とすることで、技術力と情緒的満足を融合させる新しい体験価値の構築が図られました。
組織構造の変革:「共感・自走・学習」のスクラム型チーム
最も特徴的だったのは、スクラム型組織への転換です。
これまでのような「バケツリレー型」で役割を分断する体制ではなく、研究・デザイン・PR・マーケティングなど異なる専門性を持つメンバーが“最初の問い”から一緒に関わる組織づくりに挑戦しました。
そして、野原氏自身が、最も強調したのは、この共創体制を支える「共感・自走・学習」のサイクルです。
- 共感は、心理的安全性のあるチームを築くことで、メンバーが本音で対話できる関係性を育むこと。
- 自走は、上司からの指示ではなく、チーム自身がゴールを設計し、専門性を活かして動いていくこと。
- 学習は、チームで起きる失敗について、なぜうまくいかなかったかを言語化する文化を共有し、知見を蓄積し、自分たちで修正していく力をつけていくこと。
この循環こそが、組織の持続的な変革とイノベーションのエンジンになると語られました。
リーダーシップの再定義:「自分に50%向ける」
野原氏は、スクラム型チームの基盤となる、組織におけるリーダーシップのあり方そのものの見直しにも取り組み始めています。
その取り組みの中では、従来の「管理職=管理者」ではなく、ミドルマネジメントは“支える役割(サーバントリーダー)”となり、メンバー一人ひとりの“やりたいこと”や“強み”に光を当て、それを他者貢献に変換する場づくりこそ、リーダーの役割として再定義を捉え直していることの話をされています。
また、「リーダーシップの50%は自分に向けよ」という言葉を学び、リーダー自身の在り方とモチベーションがチームの成果に直結するという、リーダーのセルフアウェアネスの重要性と、誰もが自分自身に対してセルフリーダーシップを発揮することが出来ることの大切さについても強調されました。
日々の関係性を変える「身体化された仕掛け」
抽象的なスローガンだけでは組織は変わりません。
そのため、野原氏のチームでは日々の関係性に“小さな仕掛け”を丁寧に織り込む工夫がなされました。
たとえば、新メンバーの自己紹介では「好きなもの」や「推し」を話す時間を設ける。
ブランドのゴール設定には、マーケターだけでなくパッケージデザイナーや研究職も対等に参加し、「安心感」や「清潔感」といった感情的ゴールを共に創るプロセスが重視されました。
さらに、評価制度にも「チームへの貢献」や「ナレッジの横展開」が盛り込まれ、共創と学習の文化が人事制度でも支援される構造が整備されています。
the teamの思想との交差点
野原氏の実践は、「人の可能性を引き出す組織づくり」そのものであり、the teamが掲げる以下の思想とも強く響き合います。
- 人の可能性の開花:強みへのフォーカスと自律的貢献の文化
- 組織のトランスフォーメーション:スクラム型チーム、サーバント型リーダーシップ
- 関係性の質のデザイン:感情ゴールの共創、心理的安全性の場づくり
- メタ視点の導入:組織構造そのものの再設計と“OS”の書き換え
結びに:現場から自然発生した「学習する組織」の兆し
野原氏は「組織開発の専門教育を受けたわけではない」と語られますが、
むしろそれゆえに、現場の課題から出発し、自ら学び、構造を見直し、仲間と共に進化する組織の在り方を、自然体で実現していたように見えます。
組織変革とは、掛け声でも制度設計でもなく、関係性と対話の中で育まれるもの。
そのリアルな体験を共有いただいたこの講演は、多くの参加者に勇気と示唆を与える時間となりました。


【イベントレポート②】
「企業人格」がブランドの未来を拓く
― the team株式会社 原節子 キーノート講演より(the team building day 2025)

続けて the team株式会社の共同創業者・原節子が登壇。
長きにわたって応援され、支持されるブランド構築の鍵として、“企業人格”の重要性を語りました。
なぜ、いま「企業人格」なのか?
「あなたの企業やブランドに、“魂”はありますか? “温度”は感じられますか?」
冒頭はこの問いから始まりました。
ブランドは今や、製品やサービスそのものだけでなく、それを提供する企業そのものの“人となり”=存在のあり方が問われる時代に入っています。
これは企業活動のすべてを通じて染み出る人格そのものの問いであり、これこそが今後のブランド経営の中核になると原は語ります。
ブランドの進化と、制御困難な社会構造
ブランディングは、1950年代以前から識別記号としてスタートし、次第に機能価値、情緒価値による差別化、共感、そしてパーパス(社会的存在意義)へと、その力点を移してきました。
企業がブランドの設計図を持ち、意思を持って一貫したブランディングを行うことはもちろん大切ですが、SNSをはじめとする情報発信の多様化によって、企業が自社のブランドを完全にコントロールすることは不可能な時代というのもまた事実です。
生活者や社員、投資家など多様なステークホルダーがブランドの共創者となる現在、長期にわたる信頼と共鳴を生むには、企業の内側から滲み出る人格こそが鍵を握ります。
「企業人格」とは何か? ブランドパーソナリティとの違い
ブランディングの一つの概念として「ブランドパーソナリティ」という言葉が用いられますが、これは主にブランドのトーンやスタイルといった、外から見た時の世界観として定義され、機能しているといえます。
一方、原の語る「企業人格」は、それとは異なって、組織の内側にある動機、信念、態度、文化といった“内的構造”の総体を意味します。
社員一人ひとりの内的動機や価値観が織りなす、この企業にしかない独自の在り方が、ブランドの“人となり”=企業人格として、温度感を持って世界に伝わっていくことが、これからますます重要になるのではないかという視点です。
実在の企業に見る「人格あるブランド」のかたち
講演の中では、いくつかの企業事例を挙げながら、「企業人格」の具体像を描き出しました。
たとえば、パタゴニアは「地球を救うためにビジネスを行う」という理念を掲げ、その経営判断すべてに環境配慮が貫かれています。製品・広告・行動すべてに一貫したメッセージが宿っており、「魂のあるブランド」として世界中の支持を集めています。
また、レゴは「子どもの創造性を信じる」という哲学を全製品と体験に反映させ、親子三世代にわたる共感を育んでいます。
さらに、日本企業の例として、石坂産業は、地域とのコンフリクトをきっかけに「見せる経営」へと舵を切り、見学可能な全天候型プラントのリサイクル事業や地域の里山再生等を通じて、自然と共生する循環型のライフスタイル・ソリューション・カンパニー へと変容。その姿勢はまさに、人格としての信頼を築いた例といえるでしょう。
「伝える」ではなく「伝わる」へ──企業人格の育て方
では、「企業人格」はどうやって育て、どうやって社会に届ければよいのでしょうか。
原は、「企業人格は、戦略やビジュアルだけで“作られる”ものではない」と強調します。むしろ、経営者や社員が日々の仕事の中で大切にしている価値観や信念、行動のあり方を丁寧にすくい上げ、形式知にしていくこと。そして、それを組織全体のふるまいとして日常に根づかせていくことが重要です。
それは、まさに「伝える」のではなく、「伝わる」ためのプロセス。
企業人格の実装に必要な具体的なステップとして、次の4つを挙げました:
- 経営者や社員の語る言葉に耳を傾け、その中にある「誇り」や「意味」を見つけて言語化すること
- ステークホルダーの多様な視点を取り入れ、企業の人格を立体的に描くこと
- キャッチコピーやロゴだけではなく、企業が歩んできた物語や具体的な出来事を通して語ること
- 社員一人ひとりが、企業人格を日々の判断軸として使えるように実践に落とし込むこと
こうした取り組みを重ねることで、企業は「自分たちらしさ」を軸に、パーパスや経営戦略を実現できるようになります。そこにこそ、社員や顧客、地域社会といったステークホルダーとの、深い共鳴が生まれるのです。
the team の取り組み──「関係性」から立ち上がるブランド
講演の最後に、the teamの大切にしている思想にも触れました。
「the teamが考える“企業人格”とは、人と人との関係性のなかから自然に立ち上がってくるもの。だからこそ、ブランドとは企業の“ふるまいの総体”だと私たちは捉えています」
the teamが取り組む「関係性の質を問い直す組織変容」は、そのまま企業人格の“土壌づくり”でもあります。これにより、企業の本質的な魅力や信頼性が、言葉を超えて伝わっていくのです。
結びに──「魂」と「関係性」がブランドの未来をつくる
原が本講演を通じて伝えたメッセージは、以下の通りです。
✔︎ ブランドとは、「何を大切にして、どうふるまっているか」の集積である
✔︎ 組織文化とブランドは、もはや切り離せない
✔︎ 真に応援される企業には、“人格”が感じられる
これからのブランド経営では、「成果」と「人間性」の両立が欠かせない時代になります。
the teamは、企業が自らの“ありたい姿”を内側から育てていけるよう、これからもその旅に伴走していきます。


【イベントレポート③】
社会価値と経済価値をつなぐ、“共鳴”から始まる組織変容
― サントリーホールディングス 一木典子氏 キーノート講演より(the team building day 2025)

続くキーノートとして、サントリーホールディングス株式会社の一木典子氏がご登壇。
大企業の中で社会課題と経済性の両立に挑む実践を通じて、「人と組織が変わるリアルな瞬間」をお話しいただきました。
JRからサントリーへ──“個人のパーパス”が導いた転換点
一木氏は28年間勤めたJR東日本を離れ、サントリーへとキャリアチェンジ。
その背景には、「自分の内なるパーパスに気づいてしまった」という強い衝動があったといいます。
現在は、サントリーグループにおける社会貢献活動の中核を担う部門で、「困難を抱える子ども・若者支援」や「社会的孤立」など、サステナビリティの文脈では必ずしも取り組まれることが多くはないテーマにも積極的に取り組んでいます。
サントリーに息づく“社会性のDNA”とパーパス経営の実装
サントリーの企業パーパスは、
「人と自然と響き合い、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』をめざす」。
それを実現するために、すべての社員が大切にすべき価値観は、創業以来受け継がれる「やってみなはれ」や「利益三分主義」で、事業と社会活動の両輪として実装され続けています。
一木氏はこの“生命の輝き”という言葉を軸に、社会貢献とビジネスが同じ未来を見据える状態を丁寧にデザインしています。
「人的資本」は“感情”で動く──内的動機の開花と共鳴の場
一木氏は、かつて兎洞がご一緒したワークショップの中で、昨今注目される「人的資本経営」について、次のように語りました。
“人”はコストではなく、価値を生み出す源泉。
プロジェクトやチームの熱量は、制度や戦略ではなく、現場での感情的な納得から始まる。
この前提のもと、一木氏が重視していたのが、共鳴の場=感情が動く対話の空間の設計です。
たとえば、部門横断での対話型ワークショップ、チームメンバーでの感情ベースのストーリーテリングなどを通じて、パーパスや活動方針を“自分ごと”にしていくプロセスを丁寧に作っていました。
実践①:困難を抱える若者支援──「君は未知数」プロジェクト
一木氏が中心となって推進している取組みの一つが、次世代エンパワメント活動「君は未知数」です。
これは、経済的・精神的に困難を抱える思春期の若者たちに対し、
「可能性は未知数である」というメッセージを届ける社会変革型プロジェクトです。
主な施策は次の2つ:
▪ 無料の体験提供プラットフォーム「こども冒険バンク」の開発(NPOフローレンスと共創)
- 体験格差の解消を目的に、この1年で、オンラインイベントや工場見学、ワークショップなど、6,000超の枠を無料提供。
- LINE通知で情報アクセスをサポートし、体験後には保護者・子ども双方にポジティブな心理変化が生まれる。
この取り組みは「ウェルビーイング・アワード2025 モノ・サービス部門」のグランプリを受賞し、企業とNPOが協働したモデルとしても注目されています。
▪ 思春期向けの“居場所”の質・量の拡大支援
- 思春期向けの“居場所”が、孤立や困難の予防と介入に有効との仮説を持ち、モデルとなる居場所を開設。
- 子ども食堂の年齢ギャップを補完するかたちで、「中高生が自分の都合に合わせて行けて、社会とつながれる飲食店型の子ども食堂」のあり方を模索。
共創のエコシステムを育てるための“構造づくり”
サントリーでは、こうした社会活動を「一企業のCSR部門に閉じたもの」としてではなく、「部門横断・企業横断でコレクティブインパクトを目指すもの」として捉えています。
- 社内では、部署方針に「社内関係人口の増加」や「社員との共創」を明記。
- 他企業とも共創型プロジェクトを展開し、NPO紹介セミナーをオープン化するなど、社会全体を巻き込むOSが設計されています。
一木氏はこれを「未来を共に耕すエコシステム」と表現し、企業・市民・行政・将来世代が対等に参加する共創の“土壌”づくりをリードしています。
成果の可視化と、未来への投資
このような感情や関係性をベースにした活動は、「見えにくい」とされがちですが、サントリーでは、「君は未知数」に係る活動のアウトカムとして、受益者のウェルビーイングの定点観測を行う仕組みの構築にも取組みたいと考えています。
さらに、「セオリー・オブ・チェンジ冊子」を作成・公開し、社会とのコミュニケーションを強化していく方針です。
the teamの思想との交差点
一木氏の講演は、the teamが提唱する以下の要素とも深く共鳴していたと思います。
- 人の可能性の開花:困難を抱える若者の支援と希望の可視化
- 社会構造の変容:CSRポートフォリオの再設計と企業間連携
- well-beingの循環:親子・企業・社会を巻き込む影響の連鎖
- コレクティブインパクト:社内外の関係人口を広げる社会実装戦略
結びに:“問いと共鳴”で変わる組織と社会
講演の最後に一木氏は、the teamとの協働を振り返りながらこう語りました。
「問いの質が変わると、対話の質が変わる。
対話の質が変わると、組織そのものが深く動き出す。」
NPOと企業が協働するチームづくりも同じ。組織開発とは制度設計ではなく、「納得」と「共鳴」のプロセスをいかに編んでいけるかにかかっている──
それはまさに、内的動機 × 関係性 × 社会システムという三軸で未来を再設計する、the teamの思想そのものでした。


【イベントレポート④】
「ビッグ・ウェルビーイング」から始まる創造的組織と社会の未来へ
― the team株式会社 兎洞武揚 講演より(the team building day 2025)

第一部のキーノート3名に続き、第二部では the team株式会社の共同創業者 兎洞武揚が登壇。
the team株式会社の設立趣旨や事業内容に加え、ビッグ・ウェルビーイングから始まる組織と社会の未来のあり方について語りました。
はじめに:「ビッグ・ウェルビーイング」への進化
兎洞(the team株式会社 代表取締役)は冒頭に、「ビッグ・ウェルビーイング」という新たな視座を提示しました。
これは、WHOによる従来の「身体的・精神的・社会的な健康」の定義を起点としながらも、それを個人にとどめず、社会や地球環境まで含めた包括的な幸福の在り方を意味します。
ローマクラブのレポート「アース・フォー・オール」でも示されているように、「尊厳」「つながり」「参加」「公平性」「自然」といった価値を統合した多次元指標の必要性が強調されており、個人・組織・社会・地球をつなぐ「連関の視点」こそが、次世代の組織やブランドのあり方につながると語りました。
the team創設の背景とパーパス
兎洞は、「個人が生き生きとして、組織として成果を上げながら、社会の善を実現するにはどうすればよいか?」という根本的な問いから、the teamの創業を決意したといいます。
そのパーパスは、
「一人ひとりの可能性が開花する、創造的な組織と社会を生み出すこと」。
the teamは、Big Well-beingに共感する未来志向の人や組織の「創造性パートナー」として、理念を「実装」へとつなげる場づくりと関係性のデザインに取り組んでいます。
組織が成果を出すだけでなく、社会を良化する主体として機能するには、「人がいきいきと生きること」が鍵になるとの想いが、the teamの活動を根底で支えています。
社名 “the team” に込めた意味
社名 “the team” には二重の願いを込めています。
- 創造的な組織と社会をつくる仲間としての“チーム”
- この地球そのものが、本来一つの“チーム”であることが出来る、というビジョン
組織・セクター・世代・立場を超えて、「わたしたち」として共創するためのプラットフォームを目指しており、これはthe teamのすべてのプロジェクトや対話の起点となっています。
「three layers of creativity」──創造性の3つの層
兎洞は、the teamの考える創造性の定義として、以下の3つの層を提示しました。
(1)内的動機の開花と関係の質
「自分は何を大切にしているのか」「どんな生き方を望んでいるのか」、など自分についてメンバー人一人が自覚的であろうとしていること、またそうした自分を大切に思えること、さらに、その内容をメンバー間で尊重しながら共有していること。the teamは、この状態が創造への基盤になると考えています。
(2)未知からの学びと問い
the teamは、アンノウンラーニングジャーニーと呼ぶ、今まで見ていない、見えていない、場合によっては見ようとしていないことへの体験的なインプットを重視します。それは、未知にこそ、大切な気づきや学びを得る、機会があるという確信があるからです。そして、この体験と対話を通じて、本質的な課題を見出すクリエイティブ・クエスチョンが生まれます。そして、この「問い」こそが、創造的なアクションへの出発点になるのです。
(3)システムを変えるデザイン
創造とは、単線的な問題の解決ではなく、クリエイティブクエスチョンに根差したシステムを変容させていく「システミックデザイン」であると考えます。そして、それは、必然として、人・組織・社会・地球をつなげて構造的に捉えることになります。
この3つの層からなる創造性の話は、単なる概念定義ではなく、the teamがプロジェクトを進めていく際の実践的なアプローチそのものです。
ブランド設計と社会貢献の再構成
ブランド設計においても、従来の「機能→情緒→社会価値」というヒエラルキー型ではなく、以下の4軸を中心とした「動的ネットワークモデル」を提案しました。
- Watashi(私・内的動機)
- Nature(自然との関係)
- Social(社会との関係性)
- Economy(経済的構造)
この「Big Well-being Brandingモデル」は、事業や企業の存在意義を再構成する設計図であり、the teamならではの構造的支援のコアとなっています。
the teamが描く「創造的リーダーシップ」
最後に、創造的リーダーとは、自分を知り(Being)、他者と向き合い(Relating)、世界に働きかける(Doing)存在です。この3段階のスパイラルを深めることが、組織と社会の変容において欠かせないと強調します。
the teamでは、このプロセスを基盤とした人材育成プログラムの開発にも取り組んでおり、すでに複数の実践例が動き始めています。
結びに:「変革は、信頼と問いから始まる」
兎洞は最後に、次のように語りました。
「課題解決ではなく、信頼と問いを起点とした変容。わたしたちが共鳴し、学び合いながら未来を創っていく、その関係性こそが、the teamの核です。」
このアプローチは、コンサルティングや施策実行支援を超えて、「関係性のデザイン」そのものを価値とする、the teamの思想を象徴しています。